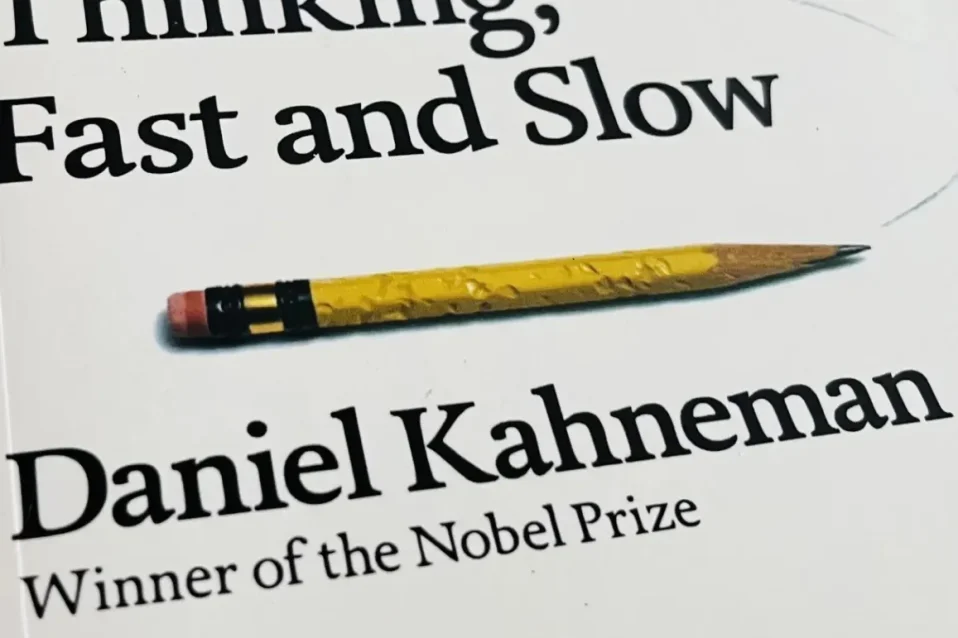
メディア・リテラシーに必要な「速い思考」と「遅い思考」
こんにちは。ふくしま新聞店の“ふくたつ”こと、福島達也です。
突然ですが、皆さんは7月20日に行われた参議院選挙の投票に行かれましたか?
近年はSNSの隆盛により、選挙活動も様変わりしました。候補者をアイドルのように“推し活”するなど政治に新しい風が吹き始めています。しかし、その反面「エコーチェンバー※1」や「フィルターバブル※2」など、自分に集まる情報に偏りが生じて多様な視点を見失ってしまうなど注意点も指摘されています。
※1エコーチェンバー・・自分と同じ意見や価値観を持つ人々の間で情報が反響し、その結果自分の意見が強化・増幅される現象のこと。
※2フィルターバブル・・自分自身が作り上げられた空間にバブル(泡)のように閉じ込められ、それ以外の情報から切り離された状態のこと。
社会の過渡期と言える今こそ「メディア・リテラシー」を高めることが重要です。それは、自分が収集した情報の成否を見極めると同時に、自分にとって、社会にとっても最善の一票を選挙で投じるという行動にいかに結びつけるか、ということです。
それを考える上で参考になる書籍があります。2002年にノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマン氏の著書「ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?」(ハヤカワ文庫刊)です。
ノーベル経済学賞を受賞した心理学者である著者が、人間の脳が情報を処理する際の特徴に基づき、「人が判断エラーに陥るパターンや理由」を明晰に解説した本書。
ここでは人間の脳が情報を処理する際の特徴として、直感に基づいて判断する「システム1」と、論理に基づいて判断する「システム2」のふたつがあることが伝えられています。人間は場面ごとに、このふたつの判断を使い分けているということです。
システム1を使っている時は、じっくり考えることはせず素早く情報を把握・判断します。そのため、手に入る全ての情報を塾考するのではなく、直感や感情などの数少ない情報を基にヒューリスティック(経験則や先入観を基にある程度正しい回答を導き出す情報処理)を使います。これをここでは「速い思考」と言い換えます。
日々たくさんの情報にさらされる私たちが生きていく上で、直感的で「速い思考」は欠かせません。カーネマンは、じつは人間の意思決定の大半はこの「速い思考」でなされているとする一方で、速い思考にのみ依存することの弊害、「ときに甚大な間違いを犯す」ことの危険性について記しているのです。
パッと見の印象にのみ流されることなく、「合理的な判断」をするためには、「遅い思考」を意識的に作動させ、事象に向き合う必要がある――
そんなカーネマンの提言にならい、今回のコラムでは、メディア・リテラシー※3を高めるために、「速い思考」と「遅い思考」をどのようにハンドリング(操作)していけば良いかと、そのための新聞の活用の仕方を含めた私のアイデアをお話します。
※3メディア・リテラシー・・・メディアの機能を理解するとともに、あらゆる形態のメディア・メッセージを調べ、批判的・多角的に分析評価し、主体的に情報を読み解く力のこと。
「速い思考」のS NSと、「遅い思考」を助ける新聞という存在
「速い思考」と「遅い思考」について、先の選挙を事例に考えてみましょう。
たとえば、選挙の候補者の主張をSNSのリール動画でみていたとします。わずか数十秒の長さでその候補者の主張を理解し、判断するのは不可能でしょう。むしろ、候補者のキャラクターなど「印象」の方が強く残ります。このような場合は人間の情報処理・判断の仕方は自動的に「速い思考」になります。
一方で、その候補者の主張を新聞で目にするとします。多岐にわたる候補者の主張をじっくり読むことで、その発言に対する整合性チェックを行うことができます。
そこには数字(データ・エビデンス)、ファクト(事実)、ロジック(論理)が存在するので、
検証もしやすく、人間の情報処理・判断の仕方は「遅い思考」になると言えるのではないでしょうか。
このように、SNS=「速い思考」新聞=「遅い思考」であると仮定した場合、重要になるのは時間の使い方です。近年の選挙活動ではSNSが大きな影響を与えています。個人が投票先を考える過程で、「主張の内容や真偽さえも熟考することなく、「直感的(速い思考)な判断に流される傾向があるのでは、という指摘は、多くのメディアでもなされています。
ただし、行動経済学者のダニエル・カールマン氏によると、人間は日常では「速い思考」で生活していて、その状態は常にオンであると言われています。「速い思考」は情報処理の上では便利かつ効率的だからです。逆に、理性的で塾考を必要とする「遅い思考」は“怠け者”でなかなか起きてこない、と言うのです。氾濫する情報へのリテラシーを高めるために、常にオン状態である「速い思考」に加えて、怠け者の「遅い思考」を如何に起動させるか。これがポイントになるでしょう。
そこで、実際に「遅い思考」のメディアである新聞を活用して、情報のインプットと投票行動の在り方を提案してみたいと思います。
「遅い思考」のメディア 新聞の役割とは
私は「SNSをみる時間の合計は常に、新聞を読む時間の半分にする」というマイルールを決めています。これは「速い思考」に対して、「遅い思考」で考える時間というリソースを多くとるためです。例えば、1日にSNSをみる時間を15分間に設定すると、新聞を読む時間は30分間になります。

SNSを15分みた後は、新聞を30分読む。これを毎回交互に繰り返すことで、「速い思考」と「遅い思考」を意識してスイッチングしています。今、自分はどちらの「思考」を用いているかを意識して読むことで、メディア・リテラシーを鍛えるトレーニングになります。
この習慣は、こと選挙という局面において、とても役立ったと考えています。候補者を知り、投票という意思決定をする重要な過程のなか、新聞というメディアが「遅い思考」を助けてくれる大切な存在となってくれたように感じるのです。
ただ、一口に新聞といっても様々なメディアが存在します。
私がここでいう新聞とは、一般社団法人日本新聞協会が「新聞倫理綱領」※4が定める、国民の「知る権利」を担保し、民主主義社会を支える役割を持ったメディアのこと。いわゆる5大新聞のほか、信濃毎日新聞、中日新聞、南信州新聞や長野日報も、同協会に所属しています。
※4一般社団法人日本新聞協会ホームページ・・・https://www.pressnet.or.jp/outline/ethics/
実際、ついSNSの「速い思考」で突っ走りそうなときに、新聞がブレーキをかけて「遅い思考」に引き戻してくれたこともありました。
今、社会全体が「速い思考」によって急速に変化しようとしています。しかし、優れた車にはアクセルの他に、よく効くブレーキが必要なように、時には「遅い思考」によって速度をコントロールしながら、上手に情報のハンドルを握っていきたいですね。







